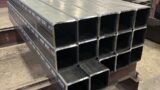この記事では、柱の組み立てを紹介します。
順序が判らない。どのように出来ていくのかを知りたい。
という方に、もっと興味をもっていただきたく思います。
柱を構成する材料を紹介します。
- コラム
- ベースプレート
- H鋼
- ダイアフラム
- 裏当て
以外に種類は少ない気がします。ただし同じ材料であっても使われる部分によって名称が変わるものもあります。少し細分化していき材料の説明をしていきたいと思います。
コラム
階層を支える部分です。木の幹のイメージですね。この階層を支える部品をシャフトと呼び階と階をくっつけて溶接で繋いでいきます。
階の梁を接続する部分で使う細切れのコラムをサイコロと呼びます。サイコロは自社ではタイコと呼ばれていて形が和太鼓に似ています。
サイコロの端部は板(DF=ダイアフラム)を溶接でくっつけて個別に加工出来るようになっています。このサイコロに梁の接続に必要な部品を付けていきます。ガセットプレートなのかH鋼を付けるのか、物件によってそれぞれ違います。
よく確認をして思い込みで間違えることがないようにしたいですね。このサイコロにつけるH鋼を仕口と呼びます。

ベースプレート
足元に当たる部品になります。柱が建った時に地面と接続をして倒れないように固定しなくてはいけません。
固定をするのにアンカーボルトと呼ばれる地面から直接出ているボルトを使用して建て込みます。アンカーボルトの設置条件に合わせてある板を溶接しておきます。
孔の中にアンカーを通してナットで締め付ける。これを柱の本数分こなしていくことになります。


上の写真はOKABEさん「ベースパック」
H鋼
梁と呼ばれる部材をH鋼から取ります。他にも母材に溶接でくっつけるH鋼は仕口と呼びます。
仕口は先程のサイコロに溶接でくっつけるために溶接しやすい形状に加工されたものを大概指します。仕口とサイコロを組み立てて個別で溶接することで後の工程を過ごしやすくします。

DF=ダイアフラム
サイコロとシャフトを繋げるための板になります。タイコの端部に溶接する材料で仕口の溶接をする部品にもなります。この板がないと仕口とサイコロとシャフトは繋がりません。

裏当て
この部品はフラットバー(通称表記はFBになります。)を、完全溶け込み溶接をするために隙間をあけた部分(この部分は開先形状と呼ばれます。)を溶接しやすいようにするためです。そもそも鉄を液体状態になるように溶かしてくっつけるのが溶接です。
液体は孔があいているとこぼれてしまいますよね。こぼれ止めの役割をします。

柱の製作工程
作図後発注をした後の話になります。
材料の受取後、規格、寸法を確認して発注書と相違がないかを確認します。
まずはサイコロを組み立てます。ここで必要な材料はサイコロ用コラムとダイアフラムと裏当てになります。

サイコロの大きさ(サイズ)は取り付ける仕口のサイズに合わせて製作をします。条件がそれぞれ違いますから、その場所場所に合わせて計画をします。その計画書を指示書と呼びます。
サイコロの溶接が終わり次は仕口の組み立てを行います。図面をよく読み内容を理解してから作業をします。仕口の組み立て後溶接をします。

シャフトに裏当てを取り付けます。この時予定している溶接隙間の分を突き出して裏当てをつけます。(突き出し部分を完全溶け込み溶接をします)裏当てを固定するためにどのような付け方をするかは人によりますが、たいていの人が治具(作業をしやすくするための道具や、台のことを指します。)を使用して精度良く取り付けます。ここでの精度とは全長の寸法と突き出した裏当てがコラムの面に対して直角についているかが重要になります。

鉄骨の柱ベースプレート(足元)を取り付けます。シャフトの1階部分に取り付ける事が多いと思いますが、たまに上階でベースプレートを使用する場合もありえますので、物件条件、に合わせて加工していきます。

この後は溶接済みの仕口とシャフトを接続していきます。この工程を大組みと呼びます。
ベースプレートから屋上(RF)までつなげていきます。

下ごしらえを済ませておいたシャフトと、溶接まで済ませておいた仕口を専用台(治具)に乗せてセットしてきます。
方向、合番を揃えていき階高、直角精度を確認します。
この時に設計寸法との誤差を確認します。
シャフトとサイコロをダイアフラムを挟んで一直線になるように調整していきます。
溶接すると製品は縮み、大曲がり等の熱による変形があります。
縮みは大きめに組むようにしていき溶接後の製品寸法が±0を目指していきます。
そのため、溶接箇所1箇所に対して+1を目安に伸ばしておきます。
溶接は対面で同じ熱量が入るように順番を確認してから作業をする必要があります。
曲がった物を矯正するには経験と時間が必要になります。
最初から曲がらないように工夫する必要があり、逆反りをつけたり、固定したりとやり方は各々あると思います。変形などが起きないように気にしながら溶接する必要があります。
大組したら溶接をして、検査を受けて合格のサインをもらいます。
検査終了後は塗装になります。
掃除をして塗り分けをします。ここでの掃除はコラムにサビが出ないように油が塗ってありますので、塗料シンナー(薄め液)を使用して脂分を除去します。油の上に塗装をしてもきれいな塗装にはならないので、余計なものは取り除きましょう。
塗装が終われば積み込みをして現場で建て方になります。
工場での工程を紹介しました。少しでも興味を持っていただけましたら幸いです。
他に色々な工程があります。是非覗いて行ってください。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。
今回はこれにて失礼します。また次回お会いいたしましょう。
こちらも覗いていただけましたら励みになります。